TEL&FAX 052-789-2662
〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町
名古屋大学教育学部教育経営学研究室
宗谷ゼミの概要
日々の活動内容

○本ゼミ
毎週の金曜日の4時限目に行っている活動です。ゼミの司会進行や議題の決定は、運営委員を中心とした学生が行い、学生が主体となって活動しています。本ゼミの主な時間は、検討会に割り当てています。8・9月の調査を控えた前期(4〜7月)は、班の問題意識や課題設定、調査でのインタビュー項目内容の検討を行います。調査後の後期(10〜1月)には、『地域教育経営に学ぶ』に掲載する論文の趣旨や章構成といった論文内容に関する検討をし、よりよい論文執筆に励んでいます。
○サブゼミ
週1回お昼の休み時間を使い、本ゼミに向けた事前検討をしています。前期には、調査の日程や飛行機・レンタカーの手配、宿泊先など、調査に向けた提案が各係となったゼミ生を中心になされ、その内容に関してゼミ生全員で検討を行います。後期は、『地域教育経営に学ぶ』に掲載している企画や特集ページの内容を、主に検討しています。また、ゼミニュースの発行時期や掲載内容の検討もサブゼミで行っています。
○分科会
調査対象ごとの班単位で行う話し合いです。分科会は検討会で受けた指摘をもとに行われ、前期は問題意識や課題設定などの書き直しやインタビュー項目の作成を行い、後期には、論文の主旨や章構成を話し合って書き直します。こうした分科会を行う中で、次回の検討会で検討をしてもらいたい箇所が明らかとなってきます。特に、後期の論文送付を控えた時期には、班員の予定を合わせて平日はほぼ毎日行っています。
宗谷ゼミの歴史
名古屋大学教育学部教育経営学講座科目として開講されている「教育経営学演習」では、主に学校づくりの実践に関する文献を用いて、文献学習を行っていました。しかし、それだけでは机上の議論に終始しがちで学問研究の意義を掴み取りがたく、大学院教育発達科学研究科教授である植田健男(当時大学院教育発達科学研究科助教授)は行き詰まりを感じていました。ちょうどその頃、植田は宗谷の実践報告を聞く機会があり、それ以来宗谷の教育合意運動に興味を抱いていました。そこで宗谷の教育合意運動をテーマとして取り上げ、1年間にわたって調査研究するという構想に至り、1992年に調査団として初めて宗谷に訪れました。研究対象に直に向かい合い、徹底してこだわる機会を提供することが学生にとって必要だと感じたのでした。これがその後長い歴史をもつことになる、「宗谷教育調査団」の発足だったのです。
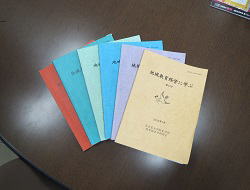
「宗谷教育調査団」の発足以降、学んだことを『宗谷教育調査報告書』としてまとめ、お世話になった方々に研究成果をお返ししてきました。発足から5年後、第五次の報告書において宗谷教育調査は1つの区切りを迎えました。 そこで、調査の新たな方向性を考えたとき、研究内容を掲載するのみでなく、ゼミの日常的な活動や調査のプロセスなども盛り込んだ、私たちの1年間の教育・研究活動のすべてを収めた冊子を新たに創刊することになりました。またその冊子には、調査を受け入れてくださっている宗谷の方々とともに考え、語り合えるような場になればとの思いも込められていました。このゼミの基本的テーマである「地域教育経営の事例検討」を意識し、教育経営学研究室の10年先、20年先を見通して『地域教育経営に学ぶ』という誌名がつけられました。この『地域教育経営に学ぶ』は1998年度以降毎年発行され、2013年度で第16号となりました。1年間のゼミ活動の集大成であり、長年の歴史を象徴する宗谷ゼミの財産とも言えるでしょう。
1992年の発足以降、現在に至るまで継続的に調査が行われてきました。調査内容に関しても、宗谷の教育合意運動や子育て運動だけでなく、各学校の教育課程や教職員集団、保護者や地域住民との共同、さらには教育行政など多岐にわたっています。これまでの宗谷教育調査団に参加した人数は、実人数で253人、延べ人数では443人にのぼります(2014年8月現在)。
こうした中で、我々と宗谷の方々との関係をお互いに学び合えるような関係にしていこうとの提案が両者からなされました。現在では宗谷と調査団の関係をさらに発展させ、宗谷での教育調査活動を宗谷の方々にとっても意義あるものとするために、さらなる研究の充実を目指しています。
information
宗谷ゼミ
〒464-8601
愛知県名古屋市千種区不老町
名古屋大学教育学部
教育経営学研究室
TEL&FAX 052-789-2662